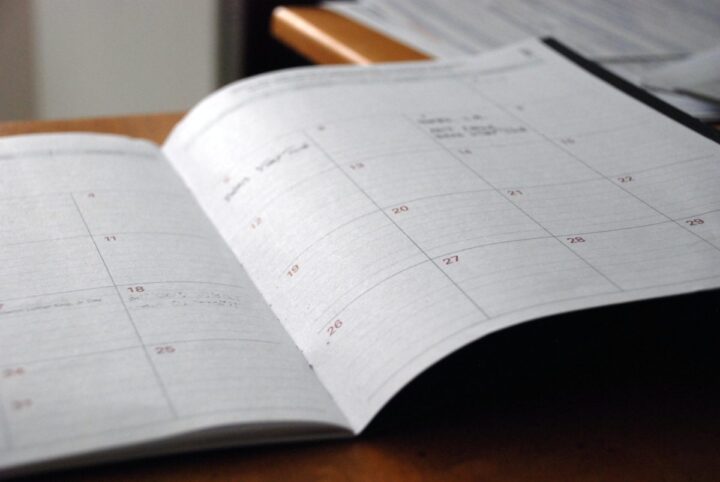こんにちは、珠子(@furatamako)です !(^^)!
運動が大切なことは、みんな知っていることです。
しかし、挫折してしまうことも多いのではないでしょうか?
自分に合った継続できる運動を見つけましょう!

ステイホームでも運動しよう!
コロナの影響で、仕事や学校・デイサービスに行けず…。
ステイホーム、モートワークでPCやスマホを操作する時間が増えました。
筋力・体力の低下を感じた人も多いのではないでしょうか?
動かなければ、「アッ」という間に筋肉は衰えてしまいます。
筋力の低下や基礎体力の低下、腸の蠕動運動低下などによって、お腹の調子も悪くなります。
その他にも転倒や骨折、心肺機能の低下など全身に影響を与えます。
そうならないように、自宅で出来る運動で筋力を維持しましょう!
スポンサーリンク
運動が腸にもたらす効果
どれだけ運動が大切か
これらは特に、消化器へ影響します。
- 気分転換・ストレス緩和、うつ病改善
- 蠕動運動を促し、便通をよくする
- 筋力の維持・向上
- 血流改善・冷え予防、体温調節
- 生活リズムを整える
ストレスで自律神経が乱れると下痢や便秘を引き起こすことが分かっています。
また、運動せずに筋力が低下するということは、腸や肛門周囲の筋肉も減少する事にも繋がるのです。
イキんでも力が入らず、排便が困難な事態に陥ります。
さらに血流も悪くなり、冷えを意識しストレスになったり、腸への栄養供給も低下し腸の機能も低下したり、気分も沈みがちになったり。
悪循環を繰り返しドンドン体調を悪化させてしまうのです・・・。
その他、運動がもたらす効果
- 骨刺激による骨の強化と骨ホルモンによる様々な効果期待
- 免疫力維持・向上
- 体力維持・増進
- カロリー消費
- 心肺機能維持・向上
- 脳の活性化、記憶力アップ
- 関節や筋肉の疼痛緩和
そのようなことにならないように、ステイホームでも適度に運動したいものです。
注意! ただし、体調や健康状況にもよりますので、運動する前に医師とご相談ください。
自宅でできる4つのおススメ運動
運動の効果が分かったところで、始めましょう!
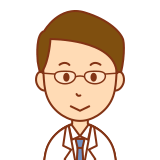
痛くない程度・気持ち良さを感じる程度で体を動かしましょう!
1. ラジオ体操
私が、過敏性腸症候群で引きこもっていた頃に、毎日行っていた「ラジオ体操」をすすめたいと思います。
【ラジオ体操第一>首の体操>ラジオ体操第二】と続けて真剣に実施したら、うっすらと汗ばみ、心地よさも感じられ、固まっていた筋肉や関節もほぐれます。

ラジオ体操の良いところは、昔からなじみがあるので覚えなくても体が勝手に動きます。
足が悪い方は、安定した椅子に座って行ってください。

椅子に座れない方も動かせるところから始めましょう。
♢ ラジオの放送時間「ラジオ体操」
ラジオやテレビから流れる「ラジオ体操」の放送時間に合わせて行っても良いですね。
生活リズムが出来るので、おすすめです。
朝・昼・晩とか朝・晩とかできたら最高です!
♢ NHKラジオの無料アプリの「らじる☆らじる」
スマホやPCでも視聴が可能だと気付きました!!!
♢ Youtube
「NHKさんのラジオ体操Youthbe」を確認したところ、NHKさんのラジオ体操がありましたのでご確認ください。
私はアナログなのでCDを購入して行っていますが、最近の情報網はすごいですね。
2. サイクルマシン
ウォーキングなどでかけられると良いのですが、在宅勤務や外出を自粛されている方へ
もう一つのおすすめは「サイクルマシン」です。
♢「サイクルマシン」って何?
リハビリや老健で使用していたコンパクトな自転車ペダル。負荷も設定できて、その人の体力に合わせられます。それは、お年寄りの方も奪い合うほど人気でした。
椅子に座って使ったり、仰臥位で使ったり、ペダル部分に手を置き肩~手の関節を動かしたりといろいろ使えます。
♢「サイクルマシン」の効果
どうやら「サイクルマシン」を漕ぐと、動きがぎこちなかった足や腕の動きも徐々に動きが滑らかになり、ストレッチ効果で苦痛が緩和されるようでした。
スポンサーリンク
「サイクルマシン」
親御さんへのプレゼントにどうでしょう?
3. スクワット
スクワットも出来たら最高ですが、無理のない程度でお願いします。
お尻を後ろに引いて、イスに座りそうで座らないような体勢をとる。
最初は、出来る範囲・曲がる範囲でスクワットし、
徐々に回数や角度を付けたスクワットをましょう!
難しいときは、手すりや安定した椅子の背もたれを持ちましょう。
4. かかと落とし
かかと落としもおすすめです。上記の運動の効果で少し触れました「骨ホルモン」。
最近の岡山大学歯学部の研究で分かってきたことがあります。
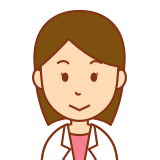
骨ホルモンの効果
“骨が作る若返り物質”が運動で増える?!
最近になって、骨に力をかけると、新しく骨を作る細胞が増えてくるだけでなく、それらの細胞がオステオカルシンを作るタイミングが早まることが分かりましたし、これらの微量成分は、骨から溶け出して全身の臓器に働きかけるメッセージ物質としても機能していることが分かってきました。例えば、オステオポンチンは免疫系に、オステオカルシンは脳、精巣、 筋肉、膵臓などに働きかけ、免疫力、記憶力、精力、筋力などを高めたり、糖代謝を調節したりすると考えられています。
今後さらに研究が進んで、骨と運動という観点から、私たちが超高齢化時代を健康で若々しく生き抜いていくためのヒントが見つかることが期待されます。
【引用・参考元】
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔形態学分野の池亀美華准教授と岡村裕彦教授、朝日大学歯学部の江尻貞一教授ら
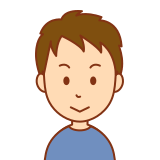
骨ホルモンて、
打ち出の小槌みたいですね。
骨→力をかける(かかと落とし)→骨ホルモン出る
→免疫系、脳、精巣、 筋肉、膵臓などに働きかけ
→免疫力、記憶力、精力、筋力などを高めたり、糖代謝を調節したりする。
かかと落としをすると、体の中で一番大きい足の骨に力がかかり、大きな効果が得られます。
※ただし、自転車やサイクルマシンでは、骨には力がかかりません。そして、クッションの良く効いた靴も力が伝わりにくいので効果が薄いです。
♢ かかと落としの方法
NHK「ためしてガッテン!」で方法を学びましょう。
※注意!膝など関節に疾患がある方、すでに骨粗しょう症の診断を受けている方、ご高齢の方などは 運動を行う前に、医師にご相談下さい。 また、転倒の恐れがある場合は行わないでください1) 姿勢をよくして、ゆっくり大きく真上に伸び上がり、ストンと一気にかかとを落とす
かかとから頭までが一直線になって動くことで、骨全体に負荷をかけることができます。頭の上から見えない糸でつり下げられているイメージで大きく真上に伸び上がりましょう。2) 1日30回以上が目標!
空いた時間にちょこちょこと行い、1日の合計が30回以上を目指しましょう。なれればもっと回数を増やしても構いませんが、1日に多くやるよりも毎日継続することの方が重要です。3) 血糖値が高めの人にオススメ
自分の骨ホルモンが多いのか少ないのかは、分かりませんが、 血糖値が高めの人はすでに骨ホルモンが少なくなっている可能性がありますので、運動とともに「かかと落とし」のような骨への刺激がオススメです。
【引用・参考元】 ためしてガッテン!より
また、
テレビでおなじみの鎌田實(諏訪中央病院名誉院長)医師が実践! 効果を得られたとおっしゃっています。
スポンサーリンク
【70歳、医師の僕がたどり着いた 鎌田式 「 スクワット 」 と 「 かかと落とし 」】
おわりに
運動は、お腹にも間違いなく大切です!
「運動の効果」でもお伝えしましたが、動くことで得られる効果は計り知れません。